3443通信 No.361
三好耳鼻咽喉科クリニック ラジオレポート
ラジオ3443通信「スギ花粉症の背景」
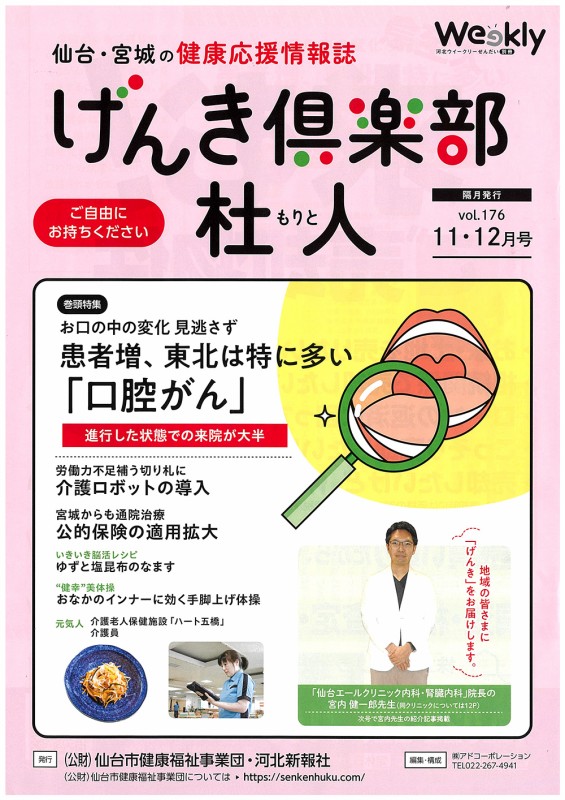
耳・鼻・喉に関する病気を扱う「三好耳鼻咽喉科クリニック」の三好彰院長は、耳鼻咽喉の診療に携わって45年。今回は2015年1月にfmいずみで放送された内容を紹介します。
[An.…江澤アナウンサー、Dr.…三好院長]
スギ花粉症の背景
An.
前回は三好先生が行ってこられたアレルギー調査のお話を伺いました。先生は北海道白老町での調査の後、栃木県旧栗山村で同様の調査を実施しておられますが、これはどういう理由からでしょうか?
Dr.
江澤さんもご存じのように、日本ではアレルギー性鼻炎の中でもスギによるそれが最も多いわけです。
An.
スギ花粉症は日本人の国民病(笑)と、聞いたことがあります。
Dr.
スギ花粉症の前は、何が日本人の国民病だったんでしょうね? 江澤さんの愛読書と、私の愛好するジブリアニメに、その最大のヒントが隠されています(笑)。
An.
それはきっと、堀辰雄の「風立ちぬ」です。サナトリウムでの孤独な生活に耐え、ヒロインがどうしても治したかった病気……思い出しました。それは結核でした。
Dr.
江澤さん。久しぶりに座布団1枚ですね。その結核が目立たなくなったのは、いつごろでしょう?
An.
江澤は肺結核のことは堀辰雄やジブリアニメでしか、知識がありませんから。かなり、以前のことかと。
Dr.
それじゃ江澤さん。逆に、スギ花粉症などのアレルギー性鼻炎が目立つようになったのは、時代的にどんな状況だったんでしょう?
An.
これは、江澤はこのOAで教えていただいた記憶があります。第2次世界大戦の後、日本は復興のために全国の山々の木々を切り倒して建築材料を確保しました。そのかいあって戦災で失われた街並みは、やがて不十分ながらも復活し、戦後の日本人の生活の役に立つようになりますが、緑に覆われていた山々は、地肌が露出しはげ山に近い状態となってしまいました。
Dr.
山の緑は生態系の保護、生物たちの住みやすい環境づくりに重要でしたけれども。それだけじゃあなくって、江澤さん?
An.
山の木々には、大雨の水をキープする「保水力」があります。台風などで大雨が降っても山が木々で覆われていれば一時的にこの木々に保持され、一気に洪水が発生することはありません。
Dr.
ということは江澤さん。はげ山は洪水が起きやすい…?
An.
戦後しばらく台風などの自然災害で、東京都など首都圏は大洪水の被害をしばしば被っていたとか。
Dr.
よくご存じですね。具体的には1947年の、カスリーン台風の例があります。約400ミリの豪雨で利根川などの堤防が決壊し、関東地方に大きな被害をもたらしました。それに対し、1950年前後に全国的にスギ・ヒノキの植林が行われ、81年の台風15号で同じ地域に同規模の豪雨が降りましたが、大きな被害は生じなかった。
An.
「治山・治水」の役に立ったスギ・ヒノキが、今度は国民病の原因になってしまった?
Dr.
原因は病気の側だけにあるわけでなく、人間側の生活環境の変動など、さまざまな要因が関わっています。日本人のアレルギー性鼻炎を研究する場合、スギ花粉症を抜きにしては議論が成り立たない。ところが白老町は北海道ですから、基本的にスギの植林がされておらず、スギ花粉症は少ないんです。
An.
それで先生は、栃木県栗山村での調査を企画された!